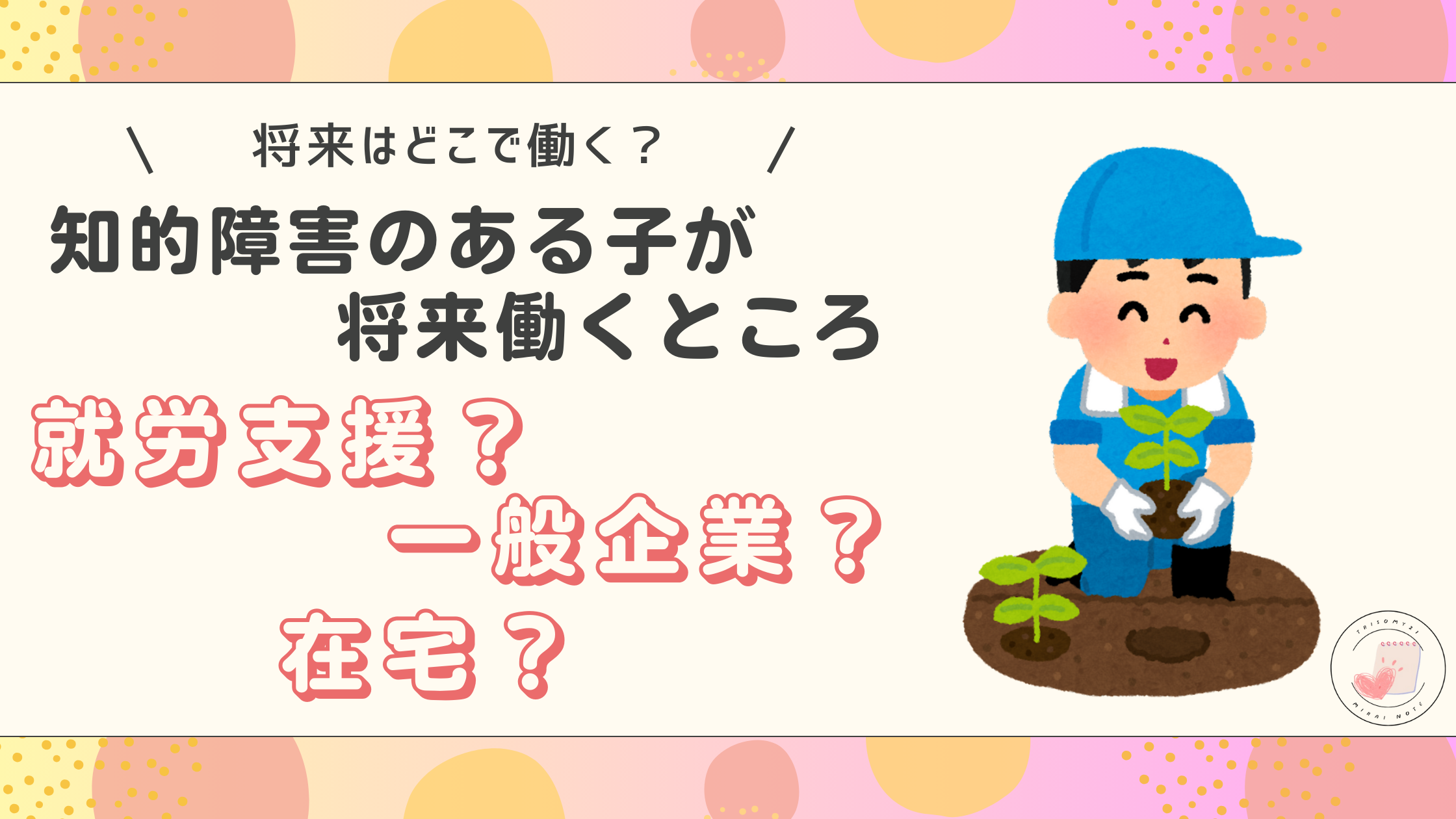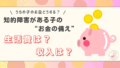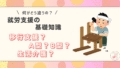この子が大きくなったら、どんな仕事ができるんだろう…?
ダウン症や知的障害のあるお子さんを育てるなかで、ふとそんなふうに思ったことはありませんか?
進路や就職のことを考えると、

働けるの?
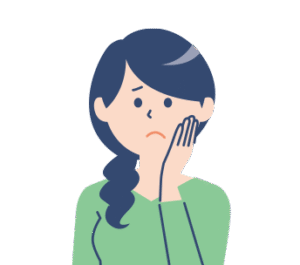
どんな選択肢があるの?

この子に合う仕事って?
――不安や疑問がどんどん浮かんできますよね。
でも、心配しすぎなくても大丈夫。
知的障害があるお子さんにも、さまざまな“働き方”があります。
この記事では、
・一般企業で働く道
・福祉的なサポートを受けながらの仕事
・自宅での働き方 など
将来の選択肢をわかりやすく整理しながら、
「わが子に合った働き方」を見つけるためのヒントをご紹介していきます。

お子さんの未来を考えるきっかけとして、ぜひ最後までご覧くださいね。
知的障害がある子の仕事には、どんな選択肢があるの?
知的障害がある子の「働き方」は、大きく分けて3つの選択肢があります。
知的障害がある子どもたちは、集中力・理解力・対人スキル・体力などにおいて特性があり、一律に「この働き方がいい」とは言えません。
ですが、今の日本にはさまざまな働き方が用意されており、「一人一人に合った働き方がきっとある」と言える時代になっています。
ここでは代表的な3つの働き方をご紹介します。
| 種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 一般企業 | ・給与や待遇が一般社員と同等のケースが多い ・社会との接点が広がる ・働く自信につながりやすい | ・環境や業務の難易度が高い場合がある ・通勤や人間関係にストレスを感じやすい ・配慮が不十分な職場もある |
| 福祉的就労 | ・支援員のサポートがある ・自分のペースで働ける ・体調や特性に合わせやすい | ・賃金が低い傾向にある(特にB型) ・仕事の選択肢が限られることがある ・「一般就労」と比べて社会との接点が少ない |
| 在宅での仕事 | ・通勤の必要がない ・得意なこと(アート、PC等)を活かしやすい ・自分のペースで働ける | ・仕事の管理やモチベーション維持が難しい場合がある ・収入の安定性に欠ける ・社会との関わりが少なくなる可能性がある |

一つずつ順番に解説していきますね。
一般企業への就労(いわゆる「障害者雇用枠」など)
一般の企業に雇用され、職場の中で働く形です。
清掃・軽作業・事務補助・接客など、職種はさまざまです。
就労移行支援などの準備期間を経て、自信をつけながら就職を目指す人も多くいます。
メリット:収入が得られ、社会的なつながりや達成感を感じられる
デメリット:働くスピードや対人関係など、一定の適応力が求められる
福祉的就労(就労継続支援A型・B型など)
支援を受けながら働ける福祉サービスを利用する働き方です。
軽作業・箱折り・農作業・施設内清掃・お弁当作りなど、できることに合わせて作業内容が用意されています。
A型は雇用契約あり、B型は雇用契約なし(工賃支給)です。
メリット:体調や特性に合わせて働ける/支援者が常にいる安心感
デメリット:収入は少なめ/就職につなげるにはステップが必要
在宅就労・創作活動など
外に出ることが難しい人でも、自宅でできる活動があります。
例:イラスト制作、ハンドメイド、ネット販売、クラウドワーク、在宅軽作業など
地域によっては支援機関とつながることで在宅でも支援を受けられる場合があります。
メリット:自分のペースで、得意なことを活かして働ける
デメリット:収入につなげるには工夫が必要/社会とのつながりが少なくなることも
このように、知的障害がある子の「働き方」にはいくつかの選択肢があります。
どの道を選ぶかは、その子の得意・苦手・安心できる環境によって異なります。
大切なのは、「何を選ぶか」ではなく、「その子に合った形で社会とつながる」こと。
いろんな選択肢を知ることで、未来への一歩が踏み出しやすくなります。
わが子に合った働き方を考えるチェックポイント
わが子に合った働き方を考えるには、特性・体調・得意なこと・サポートの必要度などを整理することが大切です。
“今のわが子の姿”を正しく理解することが、最適な進路への第一歩になります。
働き方の選択肢はいくつもありますが、すべての子に同じ方法が合うわけではありません。
特に知的障害があるお子さんの場合は、以下のような点が大きく影響します。
・一人での作業が得意か、集団の中での方が安心できるか
・体調や生活リズムが安定しているかどうか
・指示の理解や手順の記憶がどの程度できるか
・通勤や外出が苦手かどうか
・「好き」や「得意」を活かせる環境があるか
これらを見極めることで、「うちの子にはこの働き方が合いそう」という方向性が見えてきます。
以下のチェックリストを、働き方を考える一つのきっかけにしていただけたら幸いです。
簡単にできるので、お時間のあるときにチェックしてみてくださいね。
Q1:通勤や外出に抵抗はありますか?
├── いいえ → Q2へ
│
├── はい → Q7へ
Q2:集団での作業や人との関わりは比較的スムーズですか?
├── はい → Q3へ
│
├── いいえ → Q5へ
Q3:決まったスケジュールで働くことに対応できますか?
├── はい → 【一般企業就労】の可能性あり
│
├── いいえ → Q4へ
Q4:サポートがあれば働けそうですか?
├── はい → 【福祉的就労】が合うかも
│
├── いいえ → Q7へ
Q5:自分のペースで作業できる環境なら取り組めそうですか?
├── はい → 【福祉的就労】が合うかも
│
├── いいえ → Q7へ
Q7:自宅での作業なら落ち着いて取り組めそうですか?
├── はい → 【在宅就労】や【創作活動】が向いているかも
│
├── いいえ → まずは日中活動(生活介護・B型など)から体験を
チェックリストを使って“わが子の今”を見つめ直すことで、どの働き方が合いそうかが見えてきます。
もちろん、今の状態がずっと続くとは限りません。
成長や支援次第で変わっていくことも多くあります。
大切なのは、「今のわが子に無理のないスタートを選ぶこと」。
そこから少しずつ、働く力を育てていくことができます。
どの働き方にも“成長のチャンス”がある
就労の形がどんなものであっても、その子なりの成長のステージがあります。
福祉的就労であれ在宅就労であれ、「働く経験を通して人は育つ」ということに変わりはありません。
「一般就労=成功」「福祉的就労=諦め」ではありません。

次男がまだ小学部に入学したばかりの頃は、一般企業に入れた人が勝ち組だと思いこんでいました。ですが、今は全くそんなことは思いません。
それぞれの働き方に応じた成長機会や達成感があり、“その子らしさ”を大切にした就労が、結果的に一番良い選択になることも多いのです。
・できることから始めて、自信をつける
・支援の中で経験を積み、ステップアップにつなげる
・働くことで生活リズムが整い、社会との関わりが生まれる
・小さな「できた」が積み重なることで、自己肯定感が高まる
無理なく取り組める環境こそが、成長を育む土壌になります。

せっかく就労できることになっても、本人に合った環境でないと続けていくことは難しいですものね。
自分に合った環境で継続していくうちに、成長してステップアップしたり、より自分に合った働き方ができるようになった方もいます。
ここでは、3人のケースを紹介していきます。
福祉的就労から成長していくケース
B型事業所で軽作業から始めたAさん。通所を続けるうちに作業スピードが上がり、支援員と話し合ってA型にステップアップ。今ではパート契約で月10万円ほどの収入も得られるように。
在宅から「好きなこと」を活かす働き方へ
外出や人との関わりが苦手だったBさん。絵を描くのが好きで、支援員がその才能に気づき、地元イベントで作品を販売。今ではネットショップを開設し、売上も少しずつ増加中。
一般就労を目指して支援を受けながら前進
就労移行支援でビジネスマナーや清掃技術を学んだCさん。面接の練習を重ね、障害者雇用枠でホテルの客室清掃に採用され、今も継続勤務中。
どんな就労形態であっても、そこには「経験」と「成長」が詰まっています。
わが子の“今のベストな選択”をしながら、「その先」の可能性も信じて育んでいくことが大切です。
「どの働き方を選ぶか」ではなく、
「その中でどんな経験を重ねられるか」に目を向けていきましょう。
今からできること|未来の選択肢を広げるために
将来の就労に向けて、今から家庭でできる準備はたくさんあります。
ポイントは、「日常の中で」「無理なく」「楽しく」働く力の土台を育てることです。
就労準備というと「訓練しなきゃ」「何か特別なことをしなきゃ」と思ってしまいがちですが、
実は、“働く力”の多くは、生活の中で育まれます。
・決まった時間に起きる・出かける
・人の話を聞く・簡単な指示を理解する
・自分のことを自分でやる(身の回りのこと)
・手を動かして作業を続ける集中力
・できた!という経験を重ねることによる自信
これらはすべて、将来のどの働き方にも必要な「基礎力」になります。
ここでは、今から家庭でできることをいくつか紹介させていただきます。
| できること | ポイント |
|---|---|
| 生活リズムを整える | 決まった時間に起きる・寝る/食事や通院の習慣をつける |
| 家のお手伝いを習慣化 | 洗濯物をたたむ、食器を運ぶ、掃除をするなど「作業」の経験を積む |
| 興味・得意を伸ばす | 好きなことを見つけ、じっくり取り組む時間をつくる(例:折り紙、料理、パズルなど) |
| 外とのつながりをつくる | 地域の療育や放課後デイ、体験プログラムなどに参加してみる |
| 支援機関・福祉サービスの情報を集める | 就労移行、A/B型事業所、相談支援など、将来に向けた情報を早めに集めておく |
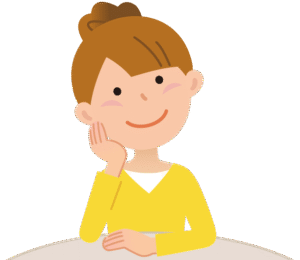
何か特別なことをしなきゃいけないと思い込んでたけど、家庭でできることもたくさんあるのね。
「就労に向けた準備」は、特別なことではなく、今の生活の中にヒントがたくさんあります。
まずは、できることを無理なく、少しずつ。
そして、“今のわが子”をよく観察して、「好き・得意・苦手」を知ることが、進路を考える第一歩です。
未来を描くことに不安があっても、
“今からできること”に目を向けると、希望の芽が見えてきますよ。

ダウン症で知的障害のある次男は最近タオルたたみのお手伝いを毎日やってくれるようになりました。きれいにたためているわけでは全くありませんが、どうせすぐに使いますし気になりません。それよりも本人が自主的に取り組もうとする「成長の芽」をこちらが摘んでしまわないように気をつけています。
まとめ:わが子らしい“働き方”は、いまから育てていける
この記事では、
・一般企業で働く道
・福祉的なサポートを受けながらの仕事
・自宅での働き方 など
将来の選択肢をわかりやすく整理しながら、「わが子に合った働き方」を見つけるためのヒントをご紹介してきました。
将来の仕事には、いろいろな形がある
知的障害のあるお子さんにも、「一般企業」「福祉的就労」「在宅での仕事」など、さまざまな働き方の選択肢があります。どれが正解というよりも、わが子に合った“その子らしい選択”ができることが大切です。
一人ひとりに合った働き方は、丁寧に探していける
「どの選択肢が合っているのか」は、すぐに決めなくても大丈夫。チェックリストを活用しながら、お子さんの特性・興味・サポートの必要度などを一緒に見つめ直していくことが、未来への第一歩になります。
今からできることが、“将来の力”になる
就労準備は、「特別な訓練」ではなく、日々の生活の中にある小さな習慣や経験の積み重ねから育っていきます。「朝起きる」「人と関わる」「お手伝いする」など、今日からでも取り組めることがたくさんあります。
どの働き方にも成長のチャンスがある
たとえ福祉的な就労であっても、安心できる環境で成功体験を積むことは大きな成長につながります。本人のペースで一歩ずつ進んでいけるよう、あたたかく見守っていきましょう。
将来に不安を感じるのは、どの親御さんも同じです。
「わが子に合った働き方がきっとある」と信じて、今できることから始めていくことが、明日の安心と笑顔につながります。
「うちの子に合った働き方ってなんだろう?」
そう思った今が、第一歩を踏み出すチャンスです。
一人一人に合った働き方を一緒に模索していきましょう。