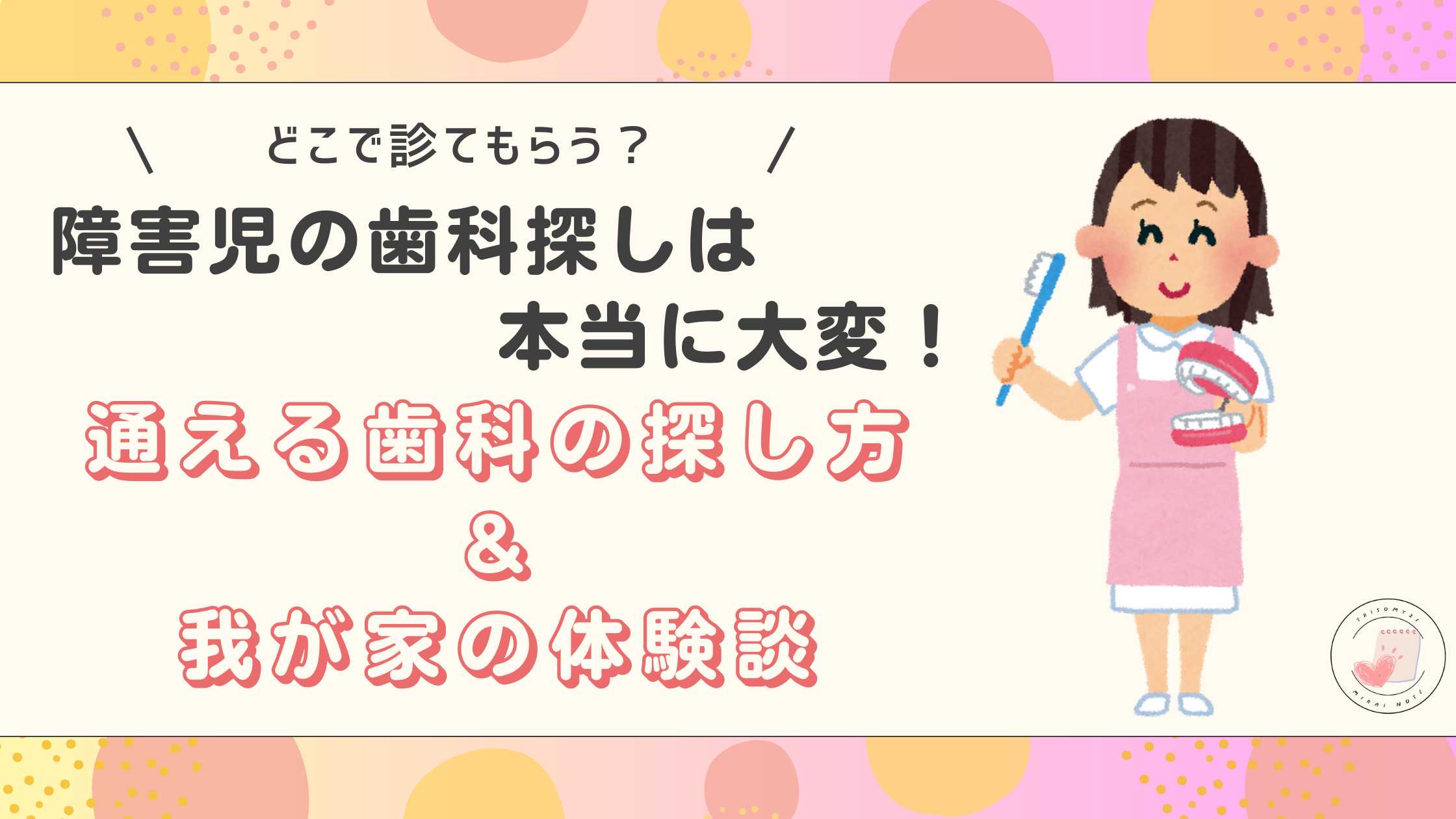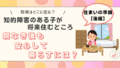うちの子、歯医者のイスにすら座れない…

口を開けられなくて、どこの歯科にも断られてしまう…
障害のあるお子さんを育てていると、そんな場面に何度も直面することがありますよね。私自身、知的障害とダウン症のある息子の歯科受診に何年も悩んできました。
押さえつけてでも治療すべき?でも、それって本当に子どものためになるの?
そんな葛藤を抱えながらも、遠回りしつつ、ようやく「息子が嫌がらずに通える歯科」に出会うことができました。
この記事では、息子がイスに座れなかった状態から一人で治療を受けられるようになるまでの道のりと、障害のある子が安心して通える歯科医院を見つけるためのポイントを、チェックリストと共にお伝えします。
同じように悩んでいる方の、歯科探しのヒントになれば幸いです。
- 障害児の歯科受診が難しい理由
- 我が家の歯科探しの経緯と治療を受けられるようになるまで
- 通える歯科を探すためのチェックリスト
なぜ障害のある子にとって、歯科受診はこんなにもハードルが高いのか?
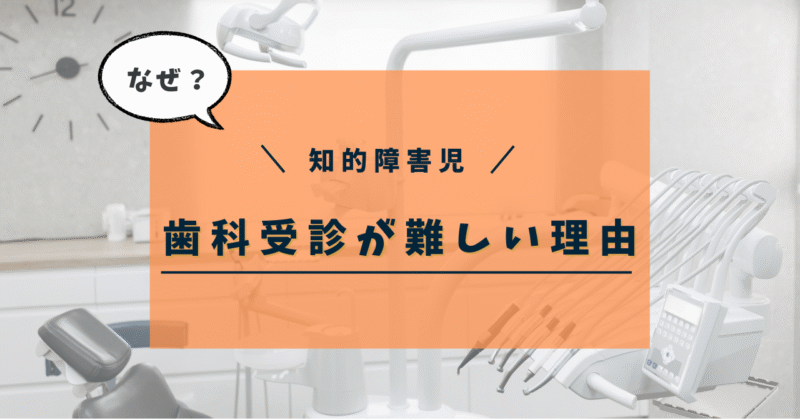
「ただ座って、口を開ける」——これが、息子にとってはとても大きなハードルでした。
特に知的障害や発達障害がある子どもにとって、歯科の診察室は五感を刺激する要素がいっぱい。
音・におい・ライトのまぶしさ・人との距離の近さ・口の中を触られる感覚…それらすべてが「怖い」と感じる子も少なくありません。
息子も最初は、イスに座るどころか、診察室に入っただけで大泣き。パニックになって暴れてしまい、診察にならなかったことが何度もありました。
また、歯科医療の現場では「限られた時間で処置をする」ことが求められるため、どうしても対応が難しい場合があります。
設備的にも、障害児への対応に慣れていない医院も多く、「申し訳ないけれど、うちでは…」と断られることも多々ありました。
一部の医療機関では「押さえつけてでも治療する」という選択肢も提案されましたが、それに抵抗感を持つ親御さんは多いはずです。
私自身、「それって息子のためになるの?」と何度も自問しました。治療を最優先すべきか、本人の気持ちを尊重すべきか——答えが出せずに悩む日々が続きました。
我が家の歯医者探し:ここまでの経緯
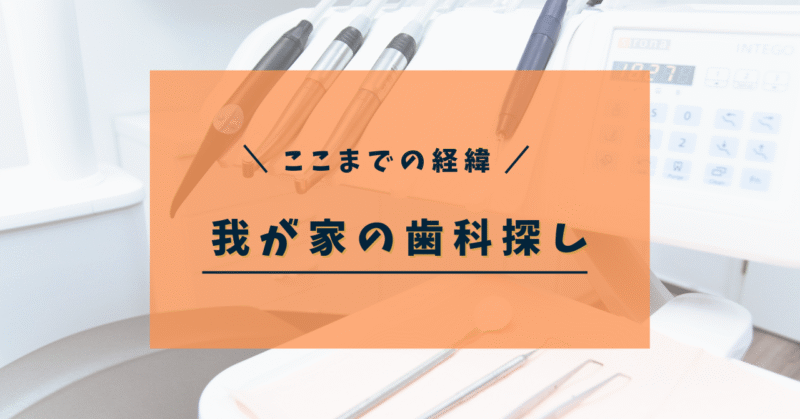
最初に通ったのは、県内でも有名な障害児専門の歯科でした。実績もあり、スタッフさんの対応もとても丁寧。でも…片道1時間半。通うだけで親子ともにぐったり。
さらに、毎回息子が暴れて治療ができず、体を拘束して開口器で口を開けてもらい治療という日々が続きました。
先生はとても手際がよく短時間で処置していただいていましたし、スタッフさんたちも親身になってくれていましたが、息子だけはどうしても治療に協力的になってくれませんでした。
拘束され、開口器を使っている治療中もずっと泣き叫ぶので、治療が終わって帰る頃には、顔や首に細かい紫斑ができ、開口器を使っているのに食いしばるものだから口の中は切れて出血、という無惨な姿で帰宅していました。
今後も治療のたびに、こんな思いをしなければならないのか?
これから先もずっとお世話にならなければならない歯医者さん、やはり近くで診てくれるところを探しておく必要があるのではないか?
という思いから、地元の歯科に片っ端から飛び込み、診てもらえるところを探し始めました。
案の定、「イスに座れないと診察できません」「うちではちょっと難しいです」と断られ続け・・・
もう無理かな・・・と諦め半分で入った今の歯科で、先生から言われた一言——
「今日は座れなくても大丈夫ですよ。少しずつ慣れていけたらいいんです。」
それを聞いた瞬間、涙が出そうになったのを今でも覚えています。
「治療ができるか」ではなく「この子のペースを尊重してくれるか」。
そこに気づいたとき、ようやく希望が見え始めました。
【時間はかかるけど確実に変わる】息子が治療を受けられるようになるまでの記録
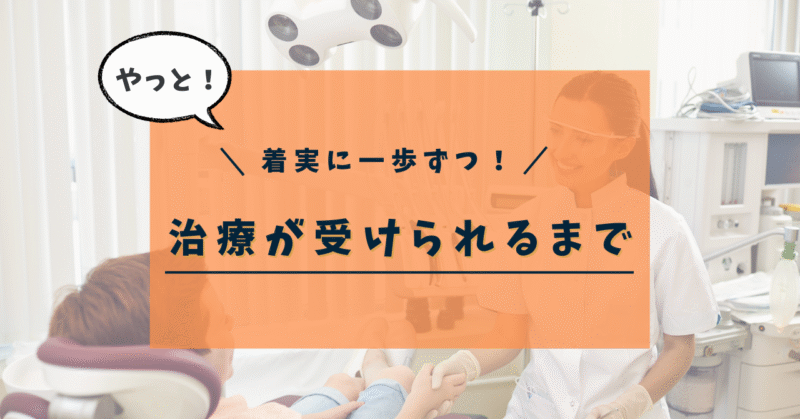
息子がその歯科に通い始めてからの1年。少しずつですが目に見える変化は、確かにありました。
- 通い始めて3ヶ月:診察室に入るだけで精一杯。イスに座ることはできませんでした。先生は無理に何かをすることなく、雑談だけで終わる日も。
- 4ヶ月目:ある日、自分からイスに座ってくれました。何もしないとわかると、徐々に安心できたようです。歯磨きだから大丈夫と言って、フッ素塗布をしてくれました
- 6ヶ月目:診察イスに座ったまま、口を軽く開けられるように。短時間でのチェックが可能に。まだ器械には抵抗があり、口には入れられませんでしたが、空気が出る器械を本人の手に当てて、「痛みはない」ということを示してくれたり、光が出る器械を「かっこいいビームやるよ、痛くないよ」と説明してくれたり、本人の気持ちが動くまで辛抱強く待ってくれました。
- 1年経過:ついに、短時間の治療が受けられるようになりました。最初のあの姿からは想像できないくらいの成長です。
時間はかかりましたが、息子が「この場所なら大丈夫」と思えたことが何よりの成果でした。
大切だったのは、「急がないで待ってくれる先生」と「焦らない親の気持ち」だったと思います。
以前の私は、「押さえつけてでも、治療を終わらせなきゃいけないんだ」と焦っていました。
でも、歯科は生涯にわたってお世話になる場所。だからこそ、本人が納得して、自分のペースで通えることが一番大事なんだと気づきました。
今は、月1回の通院を継続することが最優先。フッ素塗布やチェックだけでも大きな予防になりますし、何より「歯医者は怖くない」という安心感を積み重ねていけるのです。

本人が嫌がらずに通える歯科を見つけられたことの安心感は半端ありません
通える歯科を探すためのチェックリスト
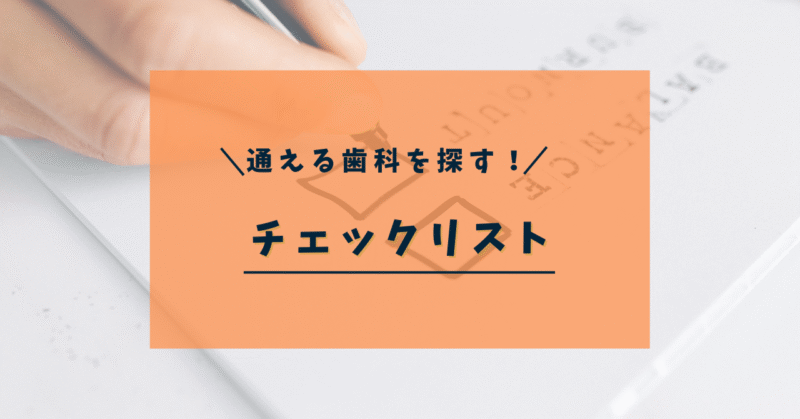

うちの子が通える歯科って、どう探せばいいの?
そんな方のために、我が家の経験をもとに作成した【チェックリスト】をご用意しました。初診前・初診時・継続通院、それぞれの場面で見るべきポイントをまとめています。
📝 《STEP1:初診前のチェックポイント》
- □ ホームページや口コミで「障害のある子の受け入れ実績」があるか
- □ 「小児歯科」「障害者歯科」の対応が明記されているか
- □ 電話で問い合わせたときに丁寧に対応してくれるか
- □ 初診前に保護者だけで見学・相談ができるか
🦷 《STEP2:初診時のチェックポイント》
- □ イスに座れない状態でも受け入れてくれるか
- □ 医師やスタッフが穏やかな対応をしてくれるか
- □ 無理に治療をせず、子どものペースに合わせてくれるか
- □ 抱っこでの診察や、イス以外の対応が可能かどうか
🗓 《STEP3:継続通院の判断ポイント》
- □ 子どもが少しずつその場所に慣れてきているか
- □ 毎回ステップアップできているか(座る→口を開けるなど)
- □ 医師との信頼関係が築けつつあると感じるか
- □ 通院後の様子が不安定すぎないか
✅ ワンポイントアドバイス:
「治療ができたか」より「また行けそうと思えるか」で評価を。
ほんの少しの前進が、将来の大きな安心につながります。
通える歯科を探している親御さんへ伝えたいこと
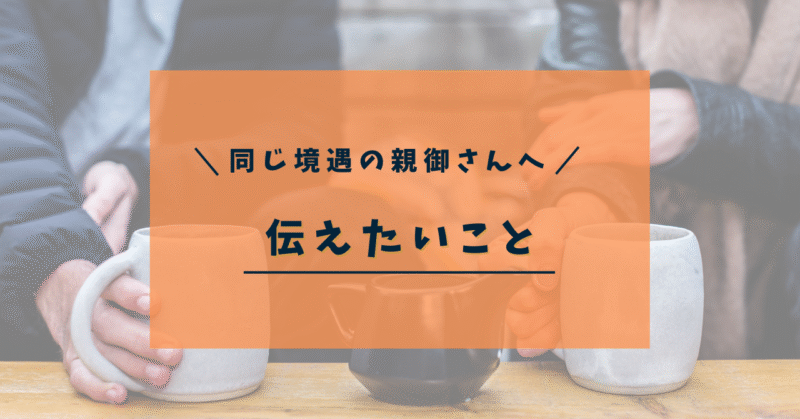
「この子に合う歯医者さんなんて、もう見つからないかもしれない」——そう思っていた私でも、今は心から信頼できる先生に出会えました。
何件も断られたって大丈夫。きっとあなたのお子さんに合う場所は、どこかにあります。
そして、親の私たちが一人で頑張りすぎなくていいということも忘れないでください。
学校や支援センター、相談支援員さん、医療ソーシャルワーカーなど、頼れる人を見つけてみてください。
疲れきってしまう前に、周りに少しだけ頼ってみる。
それも、親として大切な力の使い方だと、私は思っています。
まとめ
この記事では、
- 障害児の歯科受診が難しい理由
- 我が家の歯科探しの経緯と治療を受けられるようになるまで
- 通える歯科を探すためのチェックリスト
について紹介してきました。
障害のある子の歯科探しは、決して簡単ではありません。
でも、親子にとって「安心して通える場所」が見つかることは、人生を変えるほどの大きな安心につながります。
一歩一歩、焦らずに。小さな変化を見逃さずに。
そして、何よりも「あきらめないで」。
この経験が、同じように悩む誰かの希望になりますように。