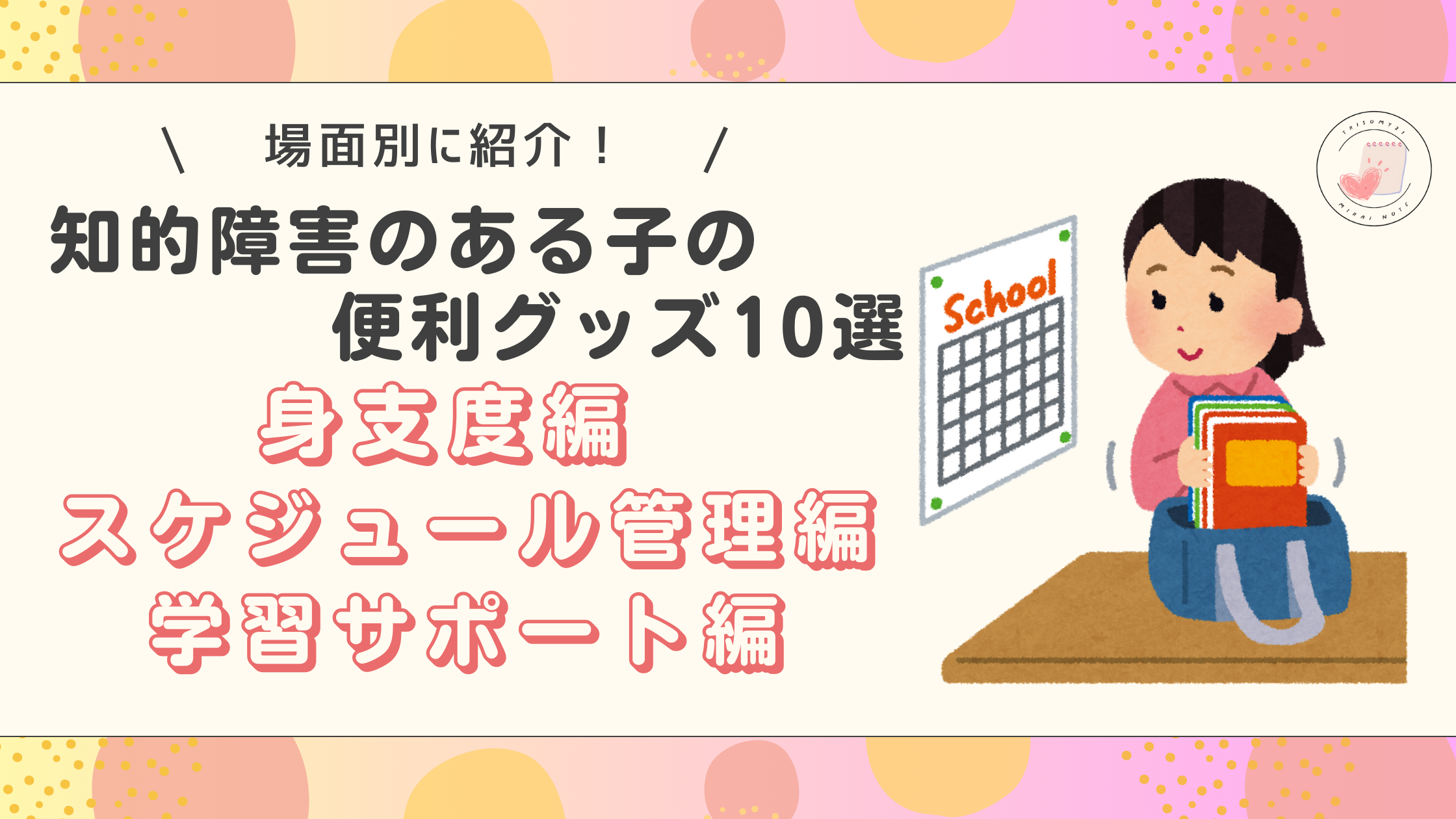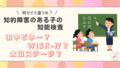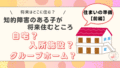朝の支度で毎日バタバタ。
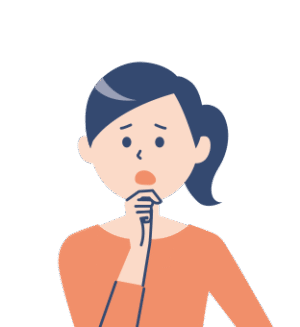
口頭だけでは次にすることがうまく伝わらず、子どもも自分もストレス。
知的障害のあるお子さんとの暮らしの中で、そんな悩みを感じることはありませんか?

我が家でも、特に朝の支度は毎朝バタバタ。息子を朝スクールバスに時間通り乗せるだけでも、1日の体力のほとんどを使ってしまっていました。
なんとか少しでも楽になりたいと、ちょっとした「便利グッズ」を取り入れたところ、日々のストレスがぐっと減り、子ども自身の「できた!」という自信にもつながったと思います。
今回は、わが家でも実際に使って役立ったアイテムを中心に、
- 身支度編
- スケジュール管理編
- 学習サポート編
の3つの場面別にご紹介します!
お子さんに合ったグッズを見つけるヒントになれば嬉しいです。
身支度編:「自分でできた!」を増やすサポートアイテム
日々の身支度をスムーズにするには、「自分でできた!」という成功体験を積み重ねることがとても大切です。
小さな成功が積み重なることで、お子さんの自信や自立心を育むことができます。
そのためには、「簡単に扱える」「失敗しにくい」便利グッズをうまく取り入れることがポイントです。
大きめサイズのスモック
動きやすく、着脱しやすい大きめサイズのスモックは、活動の自信と意欲を引き出します。
知的障害のある子どもたちは、細かい動作(ボタン留めや袖通しなど)が苦手なことがあります。
大きめサイズのスモックは、ゆったりしていて、着替えやすく、締めつけ感がないので、
作業や活動に集中しやすくなります。
- 図工や調理実習など、汚れる活動でも安心
- 自分でスムーズに脱ぎ着できるので、自己肯定感アップ
- 袖にゴムが入ったタイプなら、作業中も邪魔にならず安全

息子は小学部6年生まで、図工の時間にスモックを使っていましたが、そもそも近くのお店に大きいサイズのスモックが置いてなくて探すのに苦労しました。定型発達のお子さんは、あまり高学年までスモックを使うことはないですものね。スモックに限らず他の衣類でもそうですが、大きめサイズを選ぶのは、自分で脱ぎ着がしやすく自信に繋がるのでおすすめです。
大きめサイズのスモックは、
「自分でできた!」という達成感を支えながら、活動への意欲を引き出してくれるアイテムです。
動きやすさと着やすさを重視して選んでみましょう!
かぶるタイプの三角巾
簡単に装着できる三角巾で、給食の準備がスムーズに一人でできるようになります。
通常の三角巾は、結ぶ作業が難しかったり、ずれやすかったりします。
かぶるタイプの三角巾なら、帽子のようにかぶるだけで準備完了なので、
ハードルがぐっと下がります。
- 調理実習や給食当番、家庭でのお手伝い時に活用
- 鏡を見ながら自分でかぶれるので、自立心も育つ
- ゴム入りでフィット感があり、ずれにくく安心
かぶるタイプの三角巾は、
「サッとかぶるだけ」で、給食当番などの準備ができるサポートアイテムです。
楽しく、手軽に身につけられるものを選びましょう!

息子は長いこと給食帽を使っていましたが、中学部に上がりそろそろ三角巾にレベルアップしたいな、と思っていたところでした。しかし、三角巾は結ぶのが難しいし、何か良いものはないかな、と色々探していたところ、こんな便利アイテムがあることを知って早速取り入れました。今のところ一人でスムーズに着脱できているようです。
マジックテープ付きエプロン
簡単に着脱できるマジックテープ付きエプロンは、かぶるタイプの三角巾と同様に給食の準備などがスムーズに行えるようになります。
ひもの結び方が難しいと、エプロンをつけるだけで一苦労ですが、マジックテープ付きエプロンなら、ペタッと貼るだけで装着完了。
自分一人で準備や片付けができる達成感を味わいやすくなります。
- 調理や工作、掃除など、さまざまな場面でサッと使える
- 首まわりの調節も簡単なので、着心地がよい
- お手伝いのモチベーションアップにもつながる
マジックテープ付きエプロンは、
「自分でできる!」という経験を積み重ねる大きなサポーターです。
活動やお手伝いを楽しく、前向きにサポートしていきましょう!
スケジュール管理・見通し編:「先の見通し」で不安を減らすサポートアイテム
予定や時間の流れを「見える化」することで、子どもが安心して行動できるようになります。
知的障害のある子は、予定がわからないと不安になったり、行動を切り替えるのが難しくなりがちです。
スケジュールや時間を「目に見える形」で示してあげると、
「今は何をする時間?」「次は何があるの?」がわかり、気持ちも行動も安定しやすくなります。
ここでは、わが家でも役立っているアイテムをご紹介します。
日めくりカレンダー
「今日」を意識できるようになると、毎日の安心感がぐっと高まります。
知的障害のある子どもたちは、日にちや曜日などの感覚をつかむのが難しいことがあります。
日めくりカレンダーを使うことで、「今日は何日」「次は何がある」という見通しを持ちやすくなり、
不安の軽減や生活リズムの安定につながります。
- 毎朝カレンダーをめくって、「今日は〇月〇日」と確認できる
- 特別な予定(遠足、イベントなど)にシールを貼って楽しみにする
- 週末が近づくと、「あと〇日でお休みだね」とカウントダウン
日めくりカレンダーは、
「今日」と「これから」の見通しを持てるようになる、毎日の心強いサポーターです。
朝の習慣に取り入れて、安心できる1日のスタートを切りましょう!

我が家では子どもが小学校低学年の頃から、手作りの日めくりカレンダーを愛用しています。中学生になった今では、毎日自分でめくって「今日の日付、曜日、天気、予定」を確認してから登校するようになりました。予定を目で見て確認すると安心できるみたいなので、おすすめです!
週間カレンダー
「今週の流れ」を見える化すると、予定の変化にも落ち着いて対応しやすくなります。
1日単位だけではなく、1週間単位で予定を見渡す力を育てると、
先の見通しが立ちやすくなり、突然の予定変更にも少しずつ対応できるようになります。
- 月曜から日曜までの予定をイラストや文字でボードに貼って見える化
- 習い事や病院などの予定を目に見える形で伝えられる
- 週末のお楽しみを目標に、平日の頑張りを応援する
週間カレンダーは、
1週間を見通して、予定に対する「心の準備」を助けるアイテムです。
お子さんと一緒に予定を確認する時間を、ぜひ作ってみてくださいね!
お支度ボード・持ち物ボード
お支度ボードを使うと、自分で次の行動を確認できるようになり、朝の支度や帰宅後の流れがスムーズになります。
また、「何をするか」「何を持つか」を可視化すると、自立へのステップがぐっと近づきます。
身支度や持ち物の準備を言葉だけで伝えても、忘れてしまったり混乱したりすることがよくあります。
ボードに視覚的に示すことで、自分で確認しながら行動できるようになり、
少しずつ自立につながります。
- 「顔を洗う」「着替える」「朝ごはん」などのカードを順番に貼って次の行動を促す
- 「ランドセル」「水筒」「帽子」など持ち物カードを確認しながら準備できる
- 時間付きバージョンを使って「何時までに何をする」を視覚化
お支度ボードや持ち物ボードは、
「やることを自分で確認できる」力を育てる、大きなサポートツールです。
最初は一緒に確認しながら、少しずつ「自分でできた!」を増やしていきましょう。
タイマー
「時間を区切る」ことで、支度や行動がスムーズに進みやすくなります。
時間感覚がつかみにくい子どもにとって、「あと5分」「もうすぐ終わり」という言葉はあいまいです。
タイマーを使って「この作業は〇分以内にやる」「あと〇分で次へ進む」と視覚的に示すことで、
行動への切り替えがしやすくなります。
- 朝のお支度時間を15分でセットしてリズムを作る
- 「あと5分でお片づけ開始」と予告して、切り替え準備をする
- タイムタイマーで残り時間を見ながら支度を頑張る練習をする
タイマーは、
「あとどれくらい?」を見える形にして、子どもの行動をサポートする強い味方です。
毎日の支度や切り替え場面で、無理なく取り入れていきましょう!
予定や時間を目に見える形で伝えるだけで、子どもたちの日常はぐっとスムーズになります。
「わかる安心感」を積み重ねて、自信を育てていきましょう!
学習サポート編:「わかる!」を実感できる学びアイテム
具体物を使った学習サポートで、子どもたちの「わかった!できた!」を増やしましょう。
知的障害のある子どもたちは、
言葉や文字だけで学ぶよりも、実際に手で触れて・目で見て理解する方法が効果的です。
「数」「形」「順番」など、目に見えない概念も
具体物を使うことでグンとわかりやすくなり、学ぶ楽しさにもつながります。
算数セット
「見て、触って学ぶ」ことで、数の概念を無理なく身につけられます。
知的障害のある子どもたちにとって、
数字や量は言葉や教科書だけではイメージしにくいことがあります。
具体物を「目で見て、手で動かしながら」学ぶことで、
数の感覚を直感的に理解しやすくなります。
- おはじきを数えたり、並べたりして「1対1対応」の感覚を身につける
- ブロックを使って「5+3=8」など足し算を視覚的に理解する
- 数カードで数字と数量の対応を練習する
算数セットは、
「数を見て、触って、感じる」ことで、自然に算数の力を育てていく心強いアイテムです。
まずは遊び感覚で取り入れてみると、抵抗感なく学びにつながります!

我が家では兄姉の算数セットが家にあったので、そのお下がりを使いました。最初はブロックを重ねる競争をして、どちらが高い?低い?など遊び感覚で取り入れていました。本人に興味を持ってもらわなければ何も身につかないので、まずは楽しく取り組めることを第一に考えました。
視覚支援教材(絵カード)
絵カードを使い、「イラストや写真で伝える」ことで、理解のハードルをぐっと下げられます。
言葉だけで説明しても、内容をイメージするのが難しいことがあります。
視覚的な情報(絵や写真)を使うと、
「こういうことをするんだ」と直感的に理解しやすくなり、行動もスムーズになります。
- 「トイレ」「片づけ」など生活動作を示したカードを使って、次の行動を伝えられる
- ひらがなも表示することで文字の形に慣れることができる
- 複雑な動作も、絵カードを並べて(順番に)示すことで取り組むハードルが下がる
視覚支援教材は、
「ことばの代わりにイメージで伝える」ことができる、コミュニケーションの大切なサポートツールです。
日常生活や学習に、少しずつ取り入れていきましょう!
タイムタイマー
タイムタイマーを使った「見える時間管理」で、集中力と時間感覚を育てることができます。
スケジュール管理編でも「タイマー」の紹介をしましたが、ここでは「タイムタイマー」を取り上げていきたいと思います。
知的障害のある子にとって、時間はとても抽象的なものです。
「あと5分」と言われてもピンとこないこともあります。
タイムタイマーを使えば、残り時間を色や数字で視覚的に確認できるので、
気持ちの切り替えや、集中を維持する助けになります。
- 宿題タイムを「30分」でセットして、集中して取り組む
- 「お片付け5分間チャレンジ」など、短時間で区切ったタスク練習
- ゲームなどの残り時間をセットすることで、決められた時間を守りやすくする
タイムタイマーは、
「時間」という見えないものを可視化して、子ども自身の行動をサポートできるアイテムです。
遊びや学習に取り入れて、楽しく時間感覚を育てていきましょう!
まとめ
この記事では、日常生活がスムーズになる便利グッズについて
- 身支度編
- スケジュール管理編
- 学習サポート編
の3つの場面別にご紹介してきました。
知的障害のある子どもたちにとって、
「見える化」や「やりやすい工夫」は、安心して毎日を過ごすための大切なサポートになります。
身支度、スケジュール管理、学習サポート──
どれも最初から完璧を目指す必要はありません。
まずは、今のお子さんに合ったアイテムをひとつ取り入れてみることから始めましょう。
小さな成功体験が積み重なっていくと、
子どもたちはどんどん「自分でできる!」という自信を育んでいきます。
この記事が、
あなたとお子さんの毎日がちょっとラクに、そしてもっと笑顔になるきっかけになればうれしいです。